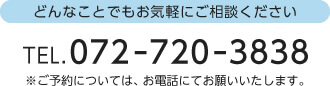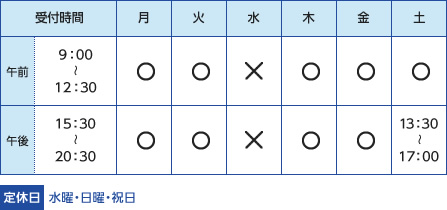足首が硬くてしゃがめない?”本当に効く”柔軟性アップの方法とは
- ホーム
- サンパーソナルタイムズ
- パーソナルトレーニング
【 お役立ちコラム 】カテゴリーを表示
2025年
11月18日
足首が硬くてしゃがめない?”本当に効く”柔軟性アップの方法とは
首が硬くて悩んでいる人って、
意外と多いんじゃないでしょうか。
足首が硬いと指摘してくれるけど、
具体的に何をしたら良いか分からないですよね。
とりあえず、ふくらはぎのストレッチ、マッサージ。
ふくらはぎ伸びてるからこんな感じかな。
それで足首が柔らかくなった、曲がるようになった、
あまり聞いたことがありません。
なので、今回は効果的な足首の使い方や柔軟性を出すものをご紹介します。
まず足首が硬いって、どういう時に感じますか?
正座すると足首の前が硬くて痛い。
しゃがむと後ろに倒れてしまい、しゃがめない。
この2つが多いかと。
しゃがめないと、
スクワットや構えの姿勢をとるのが難しくなるため、
腰を強く反ったり、膝を内側に入れたりと、
無理な使い方をして、ケガの発生率を上げてしまいます。
怪我が多い子はしゃがむのが苦手な傾向にありますので、
足首の柔軟性はやはり大事といえます。
では、ここからが本題です。
まず足首の柔軟性を上げるには
足首がどこから曲がっているかが
分からないといけません。
意外と自分の認識と違うことがあります。
その確認の仕方は足首前にできるシワです。
そこから足首が曲がる意識をして、
ストレッチするだけでも違います。
あとはストレッチする際にどこが伸びている感覚があるか。
僕はふくらはぎも大切ですが、
アキレス腱付近、足首の後ろに伸び感があるかが大事かと。
その際に足首前に出来たシワの感覚、
足首の中で骨が入っていく感覚などがあると尚良いと思います。
やり方としてはクラウチングスタートのような姿勢で

足首のストレッチをすると良いでしょう。
この時に伸ばすのは前足です。
ここでワンポイント!
カカトは浮かせて下さい!
浮かせた状態でカカトを着けにいくようにするとGOOD
あとは伸ばしながら、足の指を上げようとすると効果大!
ベンチ台や椅子などに足を乗せて行うと、
手で掴んで伸ばしたい所を伸ばせるのでオススメ!!
ぜひ、行ってみてください。
首が硬くて悩んでいる人って、
意外と多いんじゃないでしょうか。
足首が硬いと指摘してくれるけど、
具体的に何をしたら良いか分からないですよね。
とりあえず、ふくらはぎのストレッチ、マッサージ。
ふくらはぎ伸びてるからこんな感じかな。
それで足首が柔らかくなった、曲がるようになった、
あまり聞いたことがありません。
なので、今回は効果的な足首の使い方や柔軟性を出すものをご紹介します。
まず足首が硬いって、どういう時に感じますか?
正座すると足首の前が硬くて痛い。
しゃがむと後ろに倒れてしまい、しゃがめない。
この2つが多いかと。
しゃがめないと、
スクワットや構えの姿勢をとるのが難しくなるため、
腰を強く反ったり、膝を内側に入れたりと、
無理な使い方をして、ケガの発生率を上げてしまいます。
怪我が多い子はしゃがむのが苦手な傾向にありますので、
足首の柔軟性はやはり大事といえます。
では、ここからが本題です。
まず足首の柔軟性を上げるには
足首がどこから曲がっているかが
分からないといけません。
意外と自分の認識と違うことがあります。
その確認の仕方は足首前にできるシワです。
そこから足首が曲がる意識をして、
ストレッチするだけでも違います。
あとはストレッチする際にどこが伸びている感覚があるか。
僕はふくらはぎも大切ですが、
アキレス腱付近、足首の後ろに伸び感があるかが大事かと。
その際に足首前に出来たシワの感覚、
足首の中で骨が入っていく感覚などがあると尚良いと思います。
やり方としてはクラウチングスタートのような姿勢で

足首のストレッチをすると良いでしょう。
この時に伸ばすのは前足です。
ここでワンポイント!
カカトは浮かせて下さい!
浮かせた状態でカカトを着けにいくようにするとGOOD
あとは伸ばしながら、足の指を上げようとすると効果大!
ベンチ台や椅子などに足を乗せて行うと、
手で掴んで伸ばしたい所を伸ばせるのでオススメ!!
ぜひ、行ってみてください。
2025年
11月4日
足の指に力が入っていませんか?巻き爪・膝痛の原因と改善法とは

無意識で足の指に力が入っている
こんな癖がある人とても多いです!
そういう人に限って、
爪の色が黒ずんでいたり、巻き爪、
爪が丸くなり爪切りしづらいなど、
爪に症状が出やすいです。
それに膝の痛みが出ることも多い。
良いことないですね。
じゃあ、どうすれば良いか。
まず足の指を上げれるか。
その際にスネ、足首前、足の甲に力が入るか。
それが出来たら、片足立ちを足の指を上げて行えるか。
片足立ちが不安定な人ほど、足の指を握ってしまいがち。
この癖を取らないといけない。
足の指を上げると、
母趾球、小趾球、カカトが感じやすくなります。
その3点で立つことで安定性が増します。
まずはその状態で片足立ちを10秒間を
目指して行ってみてください。

本当に片足立ちが安定し、
歩きやすさが出ます!
ぜひ、お試しください!

無意識で足の指に力が入っている
こんな癖がある人とても多いです!
そういう人に限って、
爪の色が黒ずんでいたり、巻き爪、
爪が丸くなり爪切りしづらいなど、
爪に症状が出やすいです。
それに膝の痛みが出ることも多い。
良いことないですね。
じゃあ、どうすれば良いか。
まず足の指を上げれるか。
その際にスネ、足首前、足の甲に力が入るか。
それが出来たら、片足立ちを足の指を上げて行えるか。
片足立ちが不安定な人ほど、足の指を握ってしまいがち。
この癖を取らないといけない。
足の指を上げると、
母趾球、小趾球、カカトが感じやすくなります。
その3点で立つことで安定性が増します。
まずはその状態で片足立ちを10秒間を
目指して行ってみてください。

本当に片足立ちが安定し、
歩きやすさが出ます!
ぜひ、お試しください!
2025年
10月16日
「足が速くなる鍵は”ヒップロック”!初速を上げる超簡単トレーニング」
今日は足を速くするために必要なことについて
お伝えしていきます。
まず1つはヒップロックというものです。

これは前額面上での骨盤の挙上です(例、右のお尻が左のお尻より高い位置にある状態)。
この動きが出ると、地面を強く蹴ることができ、
足が前に出やすくなります。
最初の数歩で使うので、ずっとは使いませんが、
初速にはとても重要なので、
出来るようにしておきたいですね。
やり方は簡単で立った状態や膝立ちで片膝を最大限に上げる。
イメージは膝が胸に着くくらい。
すると勝手に片方のお尻が持ち上がり、
軸足のお尻に力が入ります。
あとはその感覚を濃くしたいので、
膝の上げを100%から90%の幅を行き来するように
連続で30〜50回程度行う。
すると、お尻がパンパンになります。
その感覚が掴めたら、
手を壁に着け、足を壁から離して、
腕立て伏せの姿勢になります(体は斜めの状態)。
同じように膝を上げますが、
この時、膝を前に上げるようにするのがミソ!
実際にお尻の位置が前に移動し、
手にかかる圧が強まっていればGOOD!
行っているエクササイズとしては、
ウォールドリルみたいなものです。
このエクササイズを行った後に走ると
良い感覚でスタートがとれるかと!
ぜひ、行ってみてください!
今日は足を速くするために必要なことについて
お伝えしていきます。
まず1つはヒップロックというものです。

これは前額面上での骨盤の挙上です(例、右のお尻が左のお尻より高い位置にある状態)。
この動きが出ると、地面を強く蹴ることができ、
足が前に出やすくなります。
最初の数歩で使うので、ずっとは使いませんが、
初速にはとても重要なので、
出来るようにしておきたいですね。
やり方は簡単で立った状態や膝立ちで片膝を最大限に上げる。
イメージは膝が胸に着くくらい。
すると勝手に片方のお尻が持ち上がり、
軸足のお尻に力が入ります。
あとはその感覚を濃くしたいので、
膝の上げを100%から90%の幅を行き来するように
連続で30〜50回程度行う。
すると、お尻がパンパンになります。
その感覚が掴めたら、
手を壁に着け、足を壁から離して、
腕立て伏せの姿勢になります(体は斜めの状態)。
同じように膝を上げますが、
この時、膝を前に上げるようにするのがミソ!
実際にお尻の位置が前に移動し、
手にかかる圧が強まっていればGOOD!
行っているエクササイズとしては、
ウォールドリルみたいなものです。
このエクササイズを行った後に走ると
良い感覚でスタートがとれるかと!
ぜひ、行ってみてください!
2025年
10月11日
肩こり・集中力低下の原因は”片目だけ”で見ているから?今すぐできる視力チェック法
さんは両目でモノが見えていますか?

考えたことないですよね?
過度な片目のみを利用した使い方は
視力の左右差を大きくさせ、
頭痛やめまい、首・肩コリに影響を及ぼします。
そして、集中力が持続しないことにも繋がります。
では実際にチェックしてみましょう!
右手でGOODサインを作り、親指を天井に向け、親指の爪がしっかり見えるようにします。
次に左手でも同じようにし、右手の奥に位置させます。
あとはその状態で手前の親指を見る。
その際、奥に見えている親指などが2つに見えるか。
1つに見えていたら、片目しか使えていません。
2つに見えていれば両目を上手く使えています!
次は奥の親指を見て、手前の親指が2つに見えるか。
もちろん見ている親指は1つに見えていなければなりません。
要約すると見ている物が1つで、
見えている物が2つに見えるかです。
もし上手く見えない際は、
片目を瞑って下さい。
右目の景色、左目の景色。
どちらかの景色が消えているハズです。

影の写り方が変わっているかも
片目を瞑り、消えている側の目で親指を見て、
それから両目で見ます。
片目で見た景色が両目でも見えるようになれば、
両目を上手く使えていることになります。
この使い方が出来れば、
今まで見てきたモノが少し違って見えることでしょう!
ぜひ、行ってみて下さい。
さんは両目でモノが見えていますか?

考えたことないですよね?
過度な片目のみを利用した使い方は
視力の左右差を大きくさせ、
頭痛やめまい、首・肩コリに影響を及ぼします。
そして、集中力が持続しないことにも繋がります。
では実際にチェックしてみましょう!
右手でGOODサインを作り、親指を天井に向け、親指の爪がしっかり見えるようにします。
次に左手でも同じようにし、右手の奥に位置させます。
あとはその状態で手前の親指を見る。
その際、奥に見えている親指などが2つに見えるか。
1つに見えていたら、片目しか使えていません。
2つに見えていれば両目を上手く使えています!
次は奥の親指を見て、手前の親指が2つに見えるか。
もちろん見ている親指は1つに見えていなければなりません。
要約すると見ている物が1つで、
見えている物が2つに見えるかです。
もし上手く見えない際は、
片目を瞑って下さい。
右目の景色、左目の景色。
どちらかの景色が消えているハズです。

片目を瞑り、消えている側の目で親指を見て、
それから両目で見ます。
片目で見た景色が両目でも見えるようになれば、
両目を上手く使えていることになります。
この使い方が出来れば、
今まで見てきたモノが少し違って見えることでしょう!
ぜひ、行ってみて下さい。
2025年
9月16日
「背中・腰の痛みを”土下座ポーズ”で改善!リセット呼吸法」
横になっている時間が多い方は
背中、腰に張りや痛みが出た方が多いのではないでしょうか。
原因は寝過ぎ。
動いたら良くなりますが、
即効性があるエクササイズを言うと、
土下座のポーズです。

この状態で呼吸を行うだけ!
肩が上がらずにお腹の後ろ、横が膨らむように。
正座が出来ない人は椅子に座った状態で、
太ももに肘を着けて、同じように呼吸を行うだけ。
落ち込んでいるように見えますが。笑
簡単なので、ぜひ行ってみて下さい!
横になっている時間が多い方は
背中、腰に張りや痛みが出た方が多いのではないでしょうか。
原因は寝過ぎ。
動いたら良くなりますが、
即効性があるエクササイズを言うと、
土下座のポーズです。

この状態で呼吸を行うだけ!
肩が上がらずにお腹の後ろ、横が膨らむように。
正座が出来ない人は椅子に座った状態で、
太ももに肘を着けて、同じように呼吸を行うだけ。
落ち込んでいるように見えますが。笑
簡単なので、ぜひ行ってみて下さい!